2019年7月27日(土)に秋田大学オープンキャンパスを開催しました。
理工学部1号館で各研究室の展示の他,、今年度は、数学、物理学、情報科学について、様々な疑問に答える「質問コーナーを設けました。午後からは「sinってなに?」「見てわかる計算」「エネルギーの質とは?」の3つのミニ講義を行いました。
学外のテントでは、入学試験についての相談を受け付けた他、「輪抜け」や「慣性モーメント」の体験も行いました。
多くの方にご来場いただき、ありがとうございましたました。
秋田大学理工学部 数理・電気電子情報学科
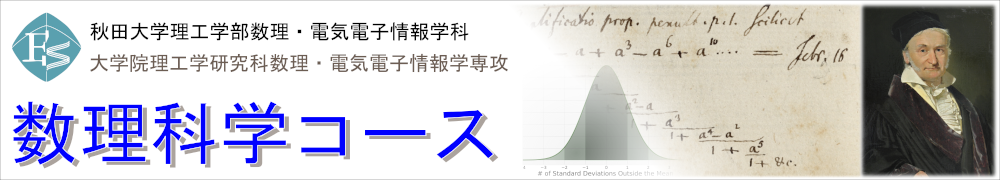
AUTOMATA2019は6月26日〜28日の3日間、メキシコ・グアダラハラのグアダラハラ大学にて開催されました。
1日目(6月25日)
成田空港からメキシコシティ国際空港を経由してグアダラハラのドン・ミゲル・イダルゴ・イ・コスティージャ国際空港へ渡航しました。日本時間25日16:35に成田空港を出発してメキシコシティ国際空港に到着したのは現地時間で25日15:20でした。18:00にメキシコシティ国際空港を出発して19:15にドン・ミゲル・イダルゴ・イ・コスティージャ国際空港に到着しました。その後ホテルに向かいチェックインをしてホテル周辺を散策しました。ホテル周辺でお祭りがあったようで賑やかな雰囲気でした。
2日目(6月26日、学会初日)
グアダラハラ大学に訪問して、学会の受付を行い、他の参加者の発表を聴講しました。空き時間でグアダラハラ大学の学内を探索しました。
夜に、学会の懇親会で夕食を食べました。
3日目(6月27日、学会2日目)
午前中に発表を行いました。午後は学会の運営者にテキーラ村を案内してもらい、観光しました。村の中はテキーラを売っている店が多く、バスの形もテキーラの酒瓶の形をしていました。メキシコのテキーラの飲み方を体験しましたが本当においしかったです。
4日目(6月28日、学会最終日)
午前中に学会が閉会しました。午後にグアダラハラを観光しました。印象に残っているのがオスピシオ・カバニャースという文化センターにある壁画と天井画廊です。
5日目(6月29日)
早朝にホテルをチェックアウトして、飛行機でメキシコシティに移動しました。
バスやタクシーを使ってテオティワカン遺跡やソカロ広場などの観光地を巡りました。
30日午前2:20にメキシコシティ国際空港を出発し、日本時間7/1日に日本に帰国しました。
感想
学会では主にセルオートマトンの内容が発表されていました。印象に残っている発表の特徴は、「どういう背景で」「何が問題で」「こんなアプローチや研究が今まであって」「このトークではこういう話をします」と、導入部が一連のスムーズな流れになっていました。そのため、話について行きやすく、最後まで夢中になって話を聞いていました。今回のスライド作成において導入部を先生から指摘されていましたが、その理由を明確に理解することができました。3日間の学会で今後の勉強や研究、スライド作成の参考になる有意義な時間を過ごすことができたと思います。
また、学会以外では観光地や料理など、日本と違う文化に触れる貴重な体験をすることができました。
海外に行くことが初めてだったので、いろいろと不安がありましたが、楽しい思い出を作ることができたと思います。
本学会参加にあたり、研究室の先生や友人には多くのご協力をいただきました。本当にありがとうございました。
数理科学コース インターンシップ進路懇話会では、主に本学の卒業生や修了生を講師としてお招きし、現在のお仕事や就職活動を含む学生時代の様子について講話を行っていただきます。進路について真剣に考え始めた学生に向けて、社会人としてのご経験を踏まえたアドバイスをいただき、数理科学を学んだ学生に対する社会や企業からの期待や要請に対する理解を深めることを目的とします。
実施日時:平成30年11月12日(月)14:30〜16:30
開催場所:理工学部7号館209室
今年度の講師(ご講演順)
菅野勇輝 氏(ヒロセ電機株式会社)
土門慎太朗 氏(三菱電機ビルテクノサービス株式会社)
佐藤達彦 氏(博士前期課程2年)
原田まな 氏(株式会社マイナビ)
平成29年5月15日(火)に、数理科学コース1年生の科目である初年次ゼミ「数理科学の世界」の中で、キャリアパス教育の一環として横手清陵学院高等学校の瀬々先生の講演が行われました。
瀬々先生が「博士号教員」として秋田に赴任するまでのお話や、研究者としてのお話、そして現在の高校教員になるためのキャリアパスから、新指導要領によって大きく変わる点などについてのお話があり、それを実感するためのグループ学習が行われました。また横手高等学校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)としての取り組みについても解説していただき,高校生に対する数理教育のこれまでとこれからについてもお話していただきました。
瀬々先生の講演のスライドは以下から見ることができます。
瀬々先生講演スライドファイル
及川貴文、柳沼孝一朗、湯本純の3名が平成30年2月21日に秋田大学教育学部主催の模擬授業フェスティバルに「数理科学3年」として参加した。
模擬授業では高校1数Iの二次関数について行った。
授業に対していただいた講評
今回いただいた講評を基に教育実習、教員採用試験に向けて学習をしていきたいと思う。
数理・電気電子情報学専攻 数理科学コースの塩原貴之が2月19日に情報処理学会東北支部で研究発表を行いました。
群知能の一つであるFirefly Algorithmをエッジ検出に適用させる研究を発表しました。学会は初めてでしたが、あまり緊張せず発表ができたと思います。また、他の方の研究もとても興味深いものが多くあり、有意義な時間を過ごせました。
(塩原貴之)
ニューラルネットワークや電子回路に関する研究が多いように印象を受けました。一番興味を引いた発表は、「危機的状況をアピールする行動を事前に定義し、その行動を検出することで、行動定義に依存しない監視カメラシステムを作る」というものがありました。
自分はニューラルネットワークの分野の研究をはじめたばかりで、この発表から自分の研究がどのうようなことができるかや研究の仕方を知ることができ、とても勉強になりました。
(平賀太竣)