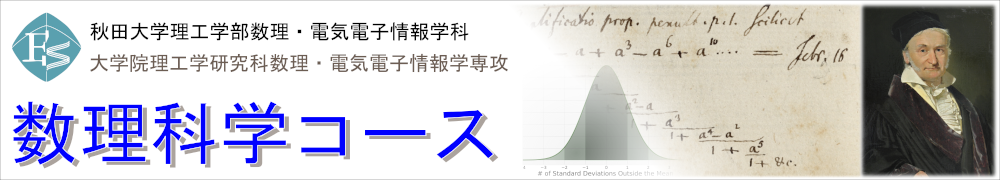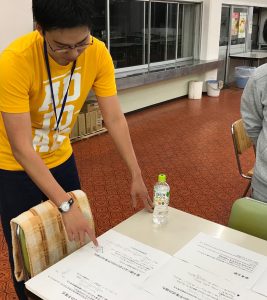10/19-21に福島県立会津自然の家(福島県河沼郡)で開催された新潟・山形地区素粒子論グループ第23回合宿研究会ポスターセッションにて,本コース理論物理学研究室三角グループ博士前期課程1年,逢坂尚人君,小原賢君,塚本尚輝君が研究発表を行いました.この研究会は新潟大学,山形大学,秋田大学,東北大学,上越教育大学の素粒子論分野の教員・学生40名ほどが参加する合宿型研究会です.
逢坂君は「量子論の非局所性とBell-CHSH不等式」と題して,量子論の非局所性に関係するBell-CHSH不等式の証明とその破れについての研究発表を行いました.特に,局所性の破れの限界点であるTsirelson boundと破れが生じるパラメータ範囲についての考察を行いました.
小原君は「AdS時空とバルク境界対応の物理」と題して,ゲージ/重力対応の例である3次元重力理論とChern-Simons理論の等価性とそこから得られる3次元反ドジッター重力理論/2次元共形場理論対応についての発表を行いました.特に,3次元反ドジッター時空の極小曲面の面積から2次元場の量子論の量子もつれエントロピーが計算される手法(笠-高柳公式)についての考察を加えました.
塚本君は「真空エネルギーの観点に基づくカシミール効果の再考察」と題して,真空の量子的エネルギーから生じる金属平行板間のカシミール力についての発表を行いました.特に,電磁場以外の場の真空エネルギーを起源とするカシミール力と無限大の発散の正則化法についての考察を加えました.
発表資料は以下で見られます.
逢坂尚人発表資料,小原賢発表資料,塚本尚輝発表資料