6月9日13:00から英国から研究活動のため訪問しているCarl-Fredrik Nyberg Broddaさんの
講演を行います。学術的な話ではなく、スウェーデンと英国の数学教育や数学の研究、留学
などについて一般的な事柄についてお話ししていただきます。ぜひご参加ください。
日時:6月9日(木)13:00(1時間程度)
場所:総合研究棟1階教室
講演者:Carl-Fredrik Nyberg Brodda(マンチェスター大学、英国)
秋田大学理工学部 数理・電気電子情報学科
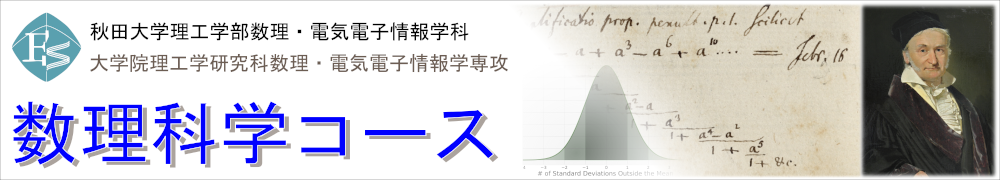
令和3年度の成績優秀者を次の通り表彰しました(以下、学籍番号順、敬称略)。
北光会賞受賞
北光会賞受賞者は、成績が優秀だった4年生の中からコース推薦された学生です。
数理科学コース成績優秀者
数理科学コースでは毎年度、2年次および4年次の後期までの通算成績が優秀だった学生が成績優秀者として表彰され、次年度の在学生ガイダンスの際に表彰状と副賞が贈られます(4年次生が就職または他大学院へ進学の場合は年度末に贈呈)。
各位のさらなるご健闘を祈ります。
山村・Fazekas 研究室の今野咲彩さん(M2)、田口輝希さん(M1)、黄新昊さん(M1)、深浦晴輝さん(B4)が、2022年2月16,17,18日に京都大学数理解析研究所で開催された研究集会「論理・代数系・言語と計算機科学の周辺領域」にて研究発表を行いました。
それぞれの研究成果を発表し、他大学の研究者とともに意見交換を行いました。
今野咲彩さんは、「Left simple and left cancellative semigroups without idempotents」のタイトルで英語で発表を行いました。
田口輝希さんは、「Correspondence between down-up alternating permutations and increasing 1-2 trees」のタイトルで発表を行いました。
黄新昊さんは、「Slightly Improved Dynamic Algorithm for LIS」のタイトルで発表を行いました。
深浦晴輝さんは、「Diagrams over groups and small cancellation conditions」のタイトルで発表を行いました。
2021年12月にNational Taiwan University(国立台湾大学)主催のオンライン講座(Fundamentals and Applications of AI Online Program)に今野咲彩さん、深浦晴輝さん、佐藤龍之介さん、清水康平さん、田口輝希さんと参加しました。オンデマンド型の講義で、AIについて学びました。
基礎理論から始まり、現在注目されている画像生成などの応用例について知ることができました。また実社会での応用としてドローンの自動操縦、建築現場での安全検査へのAI応用を学ぶことができました。オンデマンド型ということもあり、英語が苦手な僕でも何回か見直すことで問題なく受講することができました。英語はもちろんのことAIの知識も含めて、研究活動や就職活動に活かせる貴重な経験ができました。
佐藤優樹
標記の研究会にて、同研究室の湯川大地(博士前期課程2年)君と私、湯本(博士後期課程1年)が口頭発表を行いました。
今回は昨今の状況を踏まえ、2021/11/27-28にオンライン上での開催となりました。当研究会にて、湯川君は「基本表現と随伴表現を含む$R^{3} \times S^{1}$上の$SU(3)$ゲージ理論の閉じ込め相転移」、私は「グラフ理論に基づいた格子Dirac演算子の新たな解析法と$S^{4}$上における格子fermionの解析」というタイトルで発表しました。
研究会参加の所感【湯川君】
研究会参加の所感【湯本】
12月1日付で久野義人講師が着任しました。
10月1日付で板野敬太助教が着任しました。
2020年2月に開催された研究集会「代数系、論理、言語と計算機科学の周辺Ⅱ」において講演した内容をまとめたもので、星君のこれまでの研究をまとめた内容です。
Automata with One-way Jumping Mode
Kaito Hoshi, Akihiro Yamamura, Szilard Zsolt Fazekas
数理解析研究所講究録 2188巻 (2021) pp. 125-130
https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/2188-19.pdf
国際研究集会「The Fourteenth International Frontiers of Algorithmics Workshop (FAW 2020)」において発表した内容をさらに発展させてジャンピングモードを持つ2方向オートマトンの計算能力について解析しました。
Two-way deterministic automata with jumping mode
Fazekas S.Z., Hoshi K., Yamamura A.
Theoretical Computer Science 864 92 – 102 (2021)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397521001079
国際研究集会「The 25th International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems (AUTOMATA 2019) 」において発表した内容をさらに発展させてジャンピングモードがオートマトンに与える能力について解析しました。
The effect of jumping modes on various automata models
Fazekas S.Z., Hoshi K., Yamamura A.
Natural Computing (2021)
https://link.springer.com/article/10.1007/s11047-021-09844-4