ハンガリーのデブレツェン大学の研究者を招いて、最近の仕事についての短いプレゼンテーションを行うセミナーを開催します。
日時:8月30日 16:10〜17:10
場所:理工学部7号館207室
講演1
発表者 Carolin Hannusch
タイトル Algebraic code theory
講演2
発表者 Geza Horvath
タイトル Cryptosystems based on automata
秋田大学理工学部 数理・電気電子情報学科
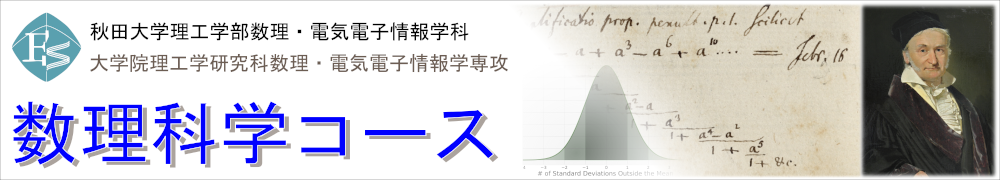
ハンガリーのデブレツェン大学の研究者を招いて、最近の仕事についての短いプレゼンテーションを行うセミナーを開催します。
日時:8月30日 16:10〜17:10
場所:理工学部7号館207室
講演1
発表者 Carolin Hannusch
タイトル Algebraic code theory
講演2
発表者 Geza Horvath
タイトル Cryptosystems based on automata
佐藤達彦君(M2)が、5月26-27日に国際教養大学で開かれた研究集会(International Workshop on Natural Computing)において、「Removal of secondary color artifacts from coring images using FCNs」の題目で深層学習を利用した地層擾乱の自動検出について発表を行いました。発表から質疑応答まで全てを英語で行うのは初めての経験であり非常に緊張しましたが、良い経験となったと思います。
セッションからは、群知能やDNA配列を元にしたアルゴリズムなど、自然計算における様々なアプローチについて学ぶことができました。学んだ内容を用いて自身の研究に活かせるよう努めていきたいと考えています。
http://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2018/06/736.php
日本物理学会誌の解説記事は,編集委員が選定した注目度・重要性の高い研究テーマについて,専門の研究者に依頼して執筆されるものです.
今回の記事では,量子論の新たな非摂動解析法であるリサージェンス理論について,三角先生が共同研究者である藤森俊明助教,坂井典佑訪問教授(慶應大)とともに解説しています.
平成29年5月15日(火)に、数理科学コース1年生の科目である初年次ゼミ「数理科学の世界」の中で、キャリアパス教育の一環として横手清陵学院高等学校の瀬々先生の講演が行われました。
瀬々先生が「博士号教員」として秋田に赴任するまでのお話や、研究者としてのお話、そして現在の高校教員になるためのキャリアパスから、新指導要領によって大きく変わる点などについてのお話があり、それを実感するためのグループ学習が行われました。また横手高等学校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)としての取り組みについても解説していただき,高校生に対する数理教育のこれまでとこれからについてもお話していただきました。
瀬々先生の講演のスライドは以下から見ることができます。
瀬々先生講演スライドファイル
平成30年度秋田こだわり木の家協議会通常総会にて「AIが導く快適な家づくり未来像」というタイトルで基調講演を行いました.
建設産業・木材産業の方々が集まる本総会での発表ということで,AIに詳しくない方にも楽しんでいただけるよう,AI研究の長い歴史の解説から始め,AIのここ最近の発展の理由や今後の応用先に関する話題までを丁寧に紹介いたしました.
講演の様子や総会の報告は秋田こだわり木の家協議会さまのHPにてもご確認できます.
http://akitakodawari.com/index2.html
平成29年度 の成績優秀者を次の通り表彰しました(以下、学籍番号順、敬称略)。
北光会賞受賞
北光会賞受賞者は、成績が優秀だった4年生の中からコース推薦された学生です。
数理科学コース成績優秀者
数理科学コースでは毎年度、2年次および4年次の後期までの通算成績が優秀だった学生が成績優秀者として表彰され、2 年生には次年度初めのガイダンスの時に、4 年生には卒業式後に、表彰状と副賞が贈られます。
各位のさらなるご健闘を祈ります。