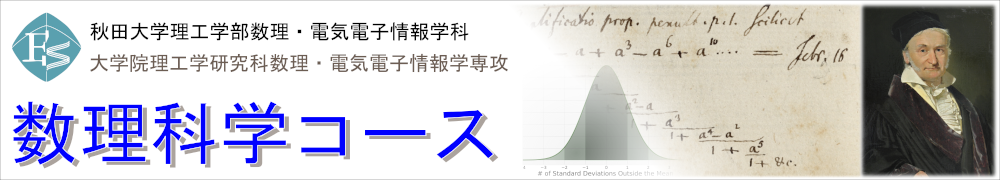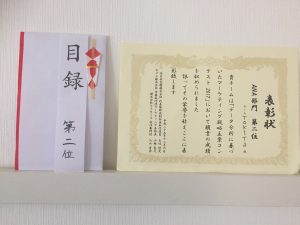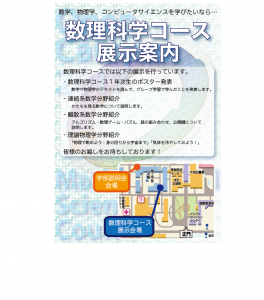津谷航平君(山村研究室・平成29年3月修士修了)が論文
「Firefly Algorithm for Uncapacitated Facility Location Problem and Number of Fireflies」
を発表しました。
数理解析研究所講究録 2051巻 pp.149-157 (2018)
研究集会「言語、論理、代数系と計算機科学の展開」で講演した内容をまとめたもので、群知能(昆虫や鳥などの集団行動を模倣した人工知能)の一つであるホタルのアルゴリズムを最適化問題である施設配置問題に応用する研究成果です。ホタルのアルゴリズムと、それに局所探索を組み入れたアルゴリズムを、最適化問題に応用した際のパフォーマンスを検討し、アルゴリズムを実行する際に最適なホタルの数について調査しました。